
次世代の研究者同士がつながり、
互いに研究発展や交流を図る
「博士の卵の会」
本学では、博士後期課程において学生による研究を支援することを目的とした「未来社会のグランドデザインを描く博士人材の育成」(Keio-SPRING)を実施しています(※)。
同プロジェクトに採択された学生の有志が自主的に情報交換や相互発表の場として「博士の卵の会」を結成し、ネットワークを広げています。その取り組み内容や、メンバーのKeio-SPRINGの活用などについてお話を伺いました。
※国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)による次世代研究者挑戦的研究プログラム[Support for Pioneering Research Initiated by the Next Generation(SPRING)]の採択・助成を得て実施
同プロジェクトに採択された学生の有志が自主的に情報交換や相互発表の場として「博士の卵の会」を結成し、ネットワークを広げています。その取り組み内容や、メンバーのKeio-SPRINGの活用などについてお話を伺いました。
※国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)による次世代研究者挑戦的研究プログラム[Support for Pioneering Research Initiated by the Next Generation(SPRING)]の採択・助成を得て実施

鈴木結子さんが作成した会のロゴ
INTERVIEWEE

佐藤 雄一郎さん
社会学研究科 D3
(2023年9月時点)
MORE
CLOSE
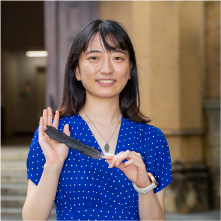
鈴木 結子さん
社会学研究科 D3
(2023年9月時点)
MORE
動物心理学に基づいたカラスの音声コミュニケーションを通し、社会性・身体性に関する研究を実施。
研究課題
都市に住む鳥類の警戒行動とヒト行動の相互関係の解明
CLOSE

小塚 太資さん
理工学研究科 D3
(2023年9月時点)
MORE
DNAや細胞で構成された「分子ロボット」の集団的な働きを制御するためのシステム論的研究。
研究課題
分子通信システムのモデル化とフィードバック制御理論の構築
CLOSE

太田 智美さん
メディアデザイン研究科 後期博士課程修了、博士(メディアデザイン学)
(2023年9月時点)
MORE
大阪音楽大学音楽学部音楽学科ミュージックビジネス専攻助教。ロボットとヒトの共生について研究。講演などの実績も豊富。
研究課題
ロボットパートナーの生活圏拡大に向けたRobot Friendlyな社会の創造
CLOSE
「博士の卵の会」を創設した代表メンバーにお集まりいただきました。
そもそもの結成のきっかけを教えてください。
- 佐藤
- 博士後期課程学生の支援として、次世代研究者挑戦的研究プログラムの採択者が一堂に会する「慶應コロキアム」というイベントがあります。活躍中の研究者の方の講演があったり、研究分野を超えた学生のセッションがあったりと貴重な交流の場ですが、開催は年に1度きりということもあり、「継続的にこういった場を設けることはできないか」と考えるようになりました。
- 小塚
- 僕たちは2022年度「慶應コロキアム」の実行委員でもあります。それまで面識がなかったところからつながったのに、これで解散ではもったいない。今後も何か一緒に活動ができないかと考え、研究交流や情報交換ができる組織を発足させ、「博士の卵の会」と名付けました。
- 鈴木
- 同じ研究科もしくは同じ専攻でも、所属研究室以外の学生とはなかなか接点を持つことがありません。せっかく同じ大学なのだから、その環境を活用したり視野を広げたりするためにも横のつながりは貴重だと感じます。
- 太田
- 採択者の一番のメリットは、多様な分野の研究者とつながれるコミュニティに参画できることだと感じています。 そのコミュニティを大事にしたいと思い、「博士の卵の会」の立ち上げに携わりました。 博士課程修了後は他大学で助教をしていますが、「博士の卵の会」があることで大学院を離れてもさまざまな分野の研究者とつながり、活動できることがとてもうれしく思います。
研究交流や情報交換することのメリットはどういった点にあるでしょうか。

- 佐藤
- 博士課程の学生にとって、目の前の研究課題に真摯に取り組もうとすると、研究費や生活費、キャリア創出の時間確保が困難になりやすい。これはおそらく皆に共通する悩みだと思っていて、他の人の状況や工夫を聞くことができると参考になります。あとは他分野の研究内容から学んだり、それが研究に役立ったりするという点がメリットです。 僕自身、鈴木さん経由で心理学専攻の教授を紹介していただいたり、設備を使わせてもらったりといったこともありました。研究に必要な機材は高額な場合が多いので、共同で使うことができると本当にありがたいです。
- 鈴木
- 佐藤さんが「“視線”の研究に関わっている教授を探している」とおっしゃっていたので、心当たりのある方を紹介させていただいたんです。すると、あっという間に意気投合されて共同研究に取り組まれていました。専門分野以外の視点が加わると研究発展に結び付きやすいですし、とても有意義だと感じました。
- 小塚
- ひとつの専門領域を深く掘り下げていると、時には行き詰ったり悩んでしまったりということもあります。しかし「博士の卵の会」に入り、同じ境遇で頑張っている仲間と出会えたことで、相談しあったり悩みを共有できたりと、視野が広がったように思います。また、「他分野ではこういった研究が行われているのだ」「こういったアプローチがあるんだ」など発見も多く、多様な世界を知ることに繋がりました。そういった意味でも、分野を超えての人脈形成は将来的なキャリアにとっても非常に有意義だと感じます。
- 太田
- 在院中は研究科のホームページやkeio.jpなど、研究に関する情報を手に入れる場所が充実していました。しかし、卒業すると同時にそういった拠り所がなくなってしまい、「一体何を見れば有益な情報を得られるのだろう?」と途方に暮れてしまったんです。その点、「博士の卵の会」は後輩たちとも情報交換ができ、加えて母校と繋がり続けることもできるとても有意義な場となっています。
「博士の卵の会」の開催内容について教えてください。
- 小塚
- メンバーは、僕たちに加え5~6人が参加しており、毎回モデレーター、担当者を決め、担当者が研究発表いただける方にオファーをして、開催は基本的にオンライン(Gather)です。未発表研究などもあるので、参加できるのは自分たちの知り合いまでというセミクローズドなスタイルに。研究発表を聞いたあとは質疑応答を含めたフリートーク的な時間を設けています。これまでに海外の大学院に留学中の方にも発表いただいたことがあるのですが、大学の奨学金システムや今後のキャリア、現地での就職に関する情報なども収集できるので、雑談の時間も有意義ですね。
- 鈴木
- これまでは1か月~2か月に1度程度開催してきました。ただ、最近は私たち3人がD3、太田さんも研究者として多忙で、なかなか活動ができていなくて。これからは同学年という横のネットワークだけではなく後輩や先輩を含めた縦のネットワークも作るなど、もう少し広げていかなければいけないなと感じています。
冒頭の話にもあったように、皆さんはKeio-SPRINGに採択されています。 この中の研究費支援はどのように活用されていますか?
- 小塚
- 僕は主に理論研究でシミュレーションが多く、ベーシックなパソコンだと精度と処理時間に限界があるため、大規模な計算機の購入をしました。高額なので、研究費の全額を投じました。
- 佐藤
- 僕も主にVRゴーグル、ウェアラブルカメラ等の機材に使って、他にも謝金や撮影した映像の文字起こし代などに活用しています。
- 鈴木
- まさに、研究機材やソフトウェアはどうしても高額なので、支給された研究費がここに消えるという人も多いようです。とはいえこれまで自分で捻出していたので、研究費で賄えるのはありがたいです。私は他にも研究地への旅費に加え、キャリア形成に必要な経費にも活用できました。申請の際は、キャリア形成に欠かせないという点を明確に説明することを意識しました。
- 太田
- 鈴木さんがおっしゃるように、書類での申請に加えて説明するというのは一つのポイントかなと思います。 私はヒトとロボットの共生について研究しており、ロボット入店可の店舗に「Robot Friendly パートナー店舗」のステッカーや冊子を配布する活動をしているのですが、これらツールの作成には当然コストがかかります。そういった説明をするため学術研究支援課に何度も足を運んだところ、結果的にスタッフの方と顔見知りの関係に。教授や友達、先輩・後輩以外の関係構築ができたことは純粋に嬉しかったです。


最後に、今後の「博士の卵の会」の運営や発展に向けて抱負をお聞かせください。
- 小塚
- 自分たちが発足人ですが、持続的な会にするためにはD1、D2の後輩たちも巻き込んで活発な活動を続けていくことが大事だなと思っています。とはいえ運営が負担になると本末転倒なので、カジュアルに集まって気軽に話しあえたりすると気分転換にもなると思います。
- 佐藤
- 自発的なコミュニティなので、マネージして発信し続けること、そして自分たちも関わり続けることは大事だと思っています。前期(修士)を入れたら大学院は5年間ありますが、長いようですごく短い。例えばD1の人がD3の人と話して今後の見通しが持てるとか、参考になる話を聞けるような発信の必要も感じています。
- 鈴木
- そうですね。他の分野の人と交流することで新たな発見があったり、研究だけにとらわれず、純粋な友達になれたりといったポジティブなことも多いと思います。ここをきっかけに仲間を作れる環境が今後続いてくれたらいいですね。
- 太田
- 少し大きな話をすると、この博士の卵の会が立ち上がる際からみんなに話していたのですが、「世界の卵の会」、つまり、世界のドクターやドクターの卵たちが集まるコミュニティを作りたい。世界各国・各地にJSTの採択者たちがいるので、そこからコミュニティをどんどんつなげていって、例えるならダボス会議のような、世界ドクターフォーラムじゃないですけど、そういったスケールの大きなものになっていけたらいいなと思います。



